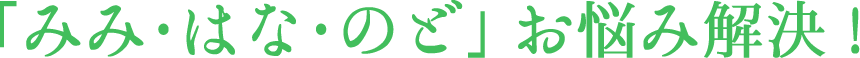
いしだ耳鼻咽喉科クリニックでは詳細な問診を行い症状・所見より原因病態を把握し、
治療の内容・期間・今後の見通しをわかりやすく説明するよう心掛けております。
 耳の病気
耳の病気子どもやご自身がかぜを引くたびに急性中耳炎を発症してしまい、病院に行くべきか悩んでいる人も多いでしょう。症状を繰り返すのは辛く、そのまま放置したり、中耳炎を繰り返したりすると生活に影響を与える可能性もあります。
万が一、耳の痛みや耳だれ、聴こえにくさがあった場合は、早めに耳鼻科を受診することが大切です。
こちらでは、急性中耳炎の症状や診断、治療法について詳しく解説していきます。急性中耳炎を予防する日常生活の過ごし方も紹介していますので、ご自身やご家族の方で急性中耳炎で困っている人は参考にしてください。
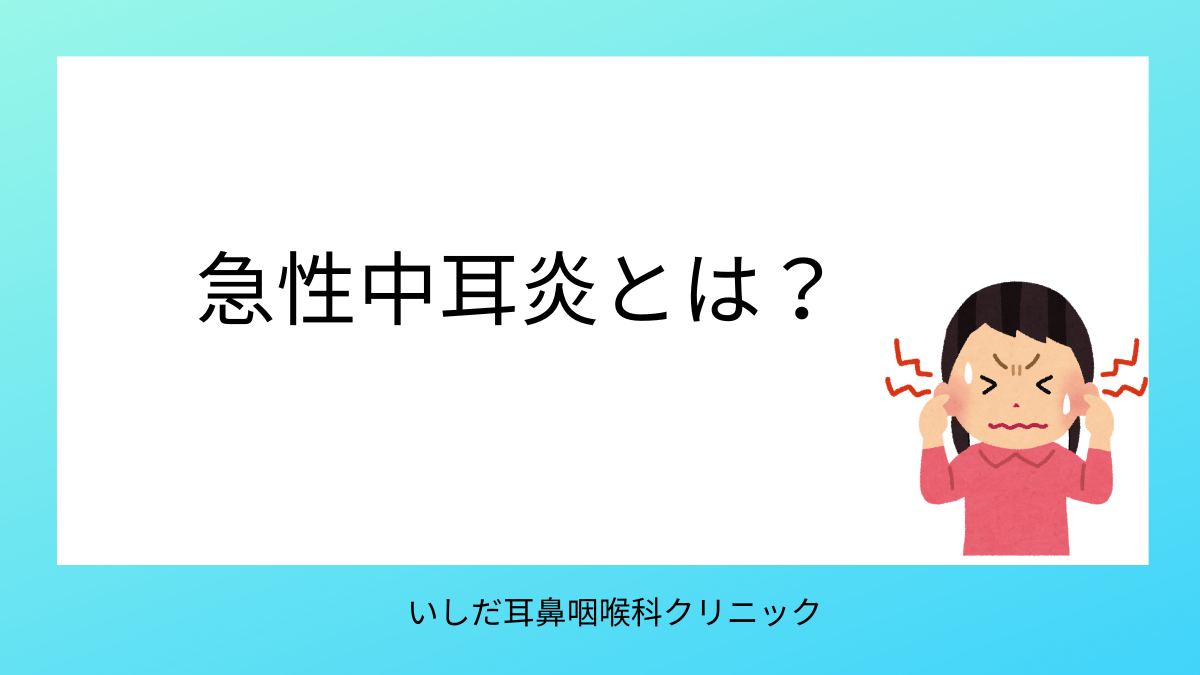
急性中耳炎は、中耳(鼓膜)が化膿して赤く腫れ、炎症を起こしている状態です。細菌やウイルスによる感染が原因で発症します。
特に生後3ヶ月から3歳頃の子どもに多く、小学校入学までに約8割の子がかかるといわれています。子どもが中耳炎にかかりやすい理由は、以下のとおりです。
かぜを引きやすい子どものうちは、急性中耳炎の発症には十分注意しましょう。
また、急性中耳炎は大人でもかかることがあります。大人の急性中耳炎は、かぜやストレス、飛行機に乗ることなどが原因です。
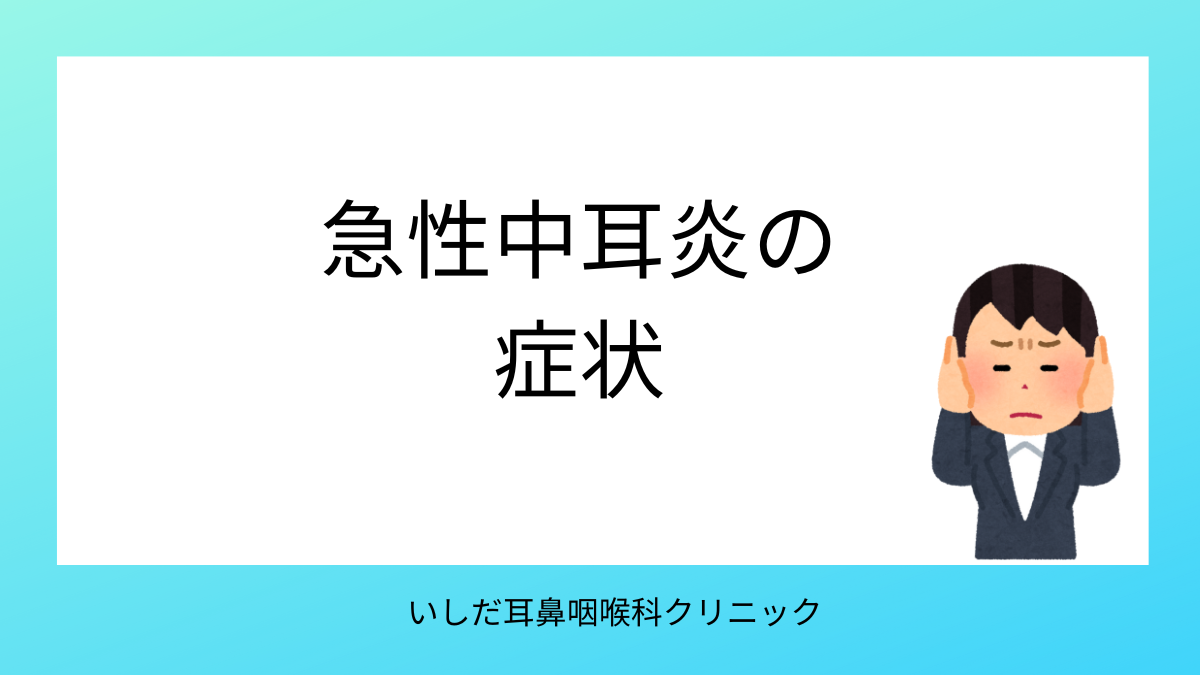
急性中耳炎の症状には以下のものがあります。
急性中耳炎になると、突然耳が痛くなります。また、耳から汁が出てくるのは、中耳に溜まった膿が多くなり鼓膜が破れるためです。膿が溜まるので、耳が詰まると難聴になって聴こえにくくなってしまいます。また、子どもの場合は熱が出やすいことも特徴です。
乳幼児は自分で症状を訴えられず、不機嫌になったり耳をさわったりといった仕草を見せます。また、耳に手を当てて泣く様子や発熱があれば、急性中耳炎の可能性を考えましょう。
子どもの急性中耳炎が悪化すると、手術の必要性や重症化のリスクがあります。 普段と様子が違う場合は、症状をよく観察しましょう。
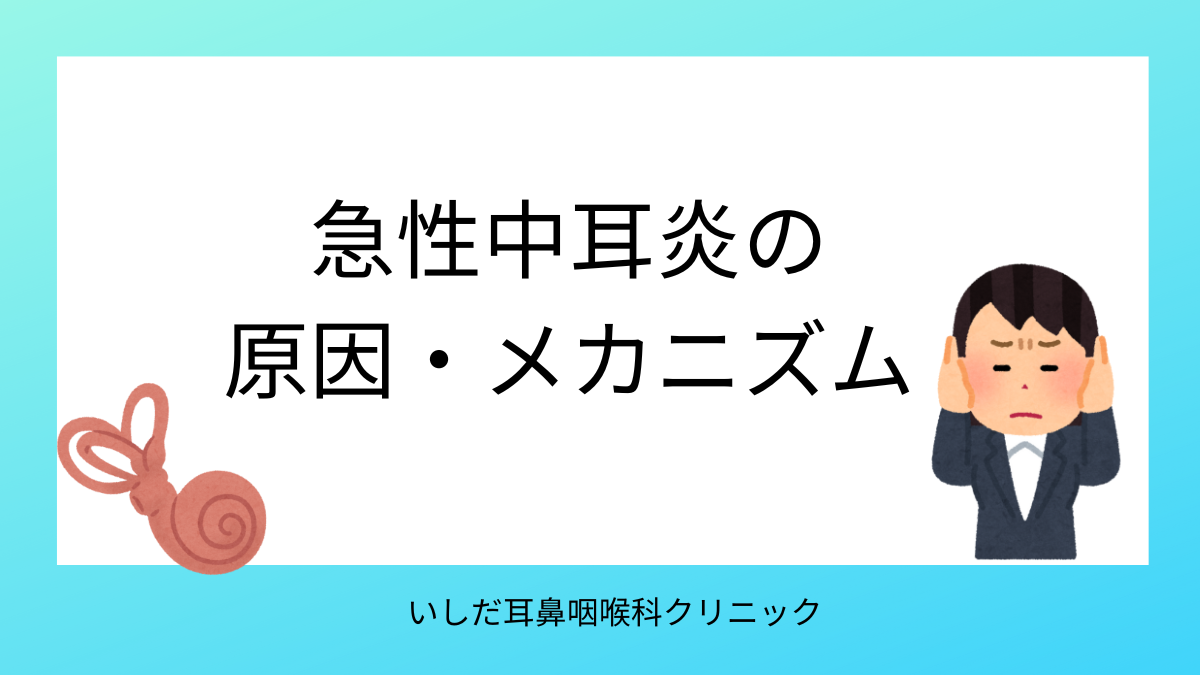
急性中耳炎の原因とメカニズムについて解説していきます。
かぜを引いた時に鼻水をすする癖や強く鼻をかんでしまうと、鼓膜内側の中耳にかぜのウイルスや細菌が侵入します。
かぜが悪化して副鼻腔炎や咽頭炎などの細菌感染を起こすと、病原体が耳管から侵入して中耳で炎症が起こり、急性中耳炎を発症します。主に、肺炎球菌やインフルエンザ菌が原因となることが多い病気です。
耳の中は、外側から外耳・中耳・内耳の3つに分けられます。鼓膜の奥に、中耳で囲まれた中耳腔があり、中耳は耳管という管で鼻の奥とつながっている構造です。
鼻水とともに細菌やウイルスが耳管を通って炎症をおこし、中耳腔に膿が溜まると急性中耳炎を発症します。
子どもが中耳炎を発症しやすいのは、大人の耳管と比べると太くて短いことが理由です。耳管の角度が、大人は斜めに傾いているのに対して、子どもはほぼ水平で、細菌やウイルスが中耳に侵入しやすい状態になります。
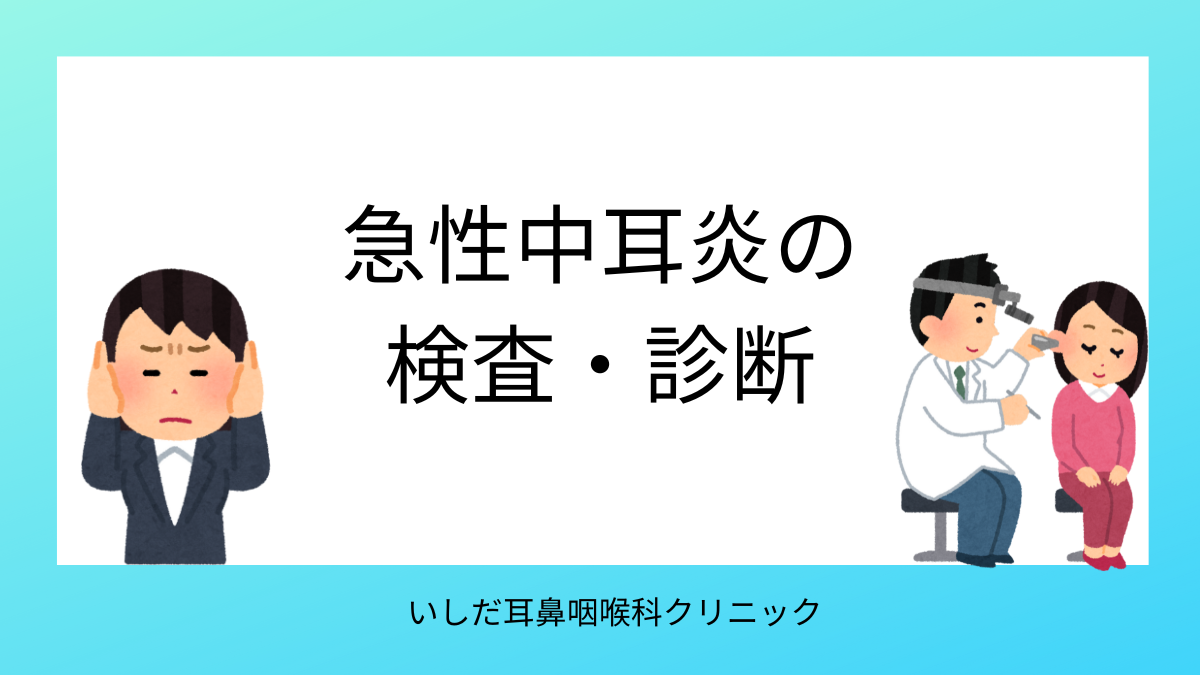
急性中耳炎の診断には、鼓膜を観察する検査が必要です。内科や小児科にはない機器が多く、診断するために耳鼻科を受診しましょう。急性中耳炎の検査方法や診断方法について解説していきます。
鼓膜鏡や内視鏡は、鼓膜内に液体がたまっているかどうかを観察し、急性中耳炎を診断する検査機器です。鼓膜の症状を確認すべき疾患が疑われるときに使用します。
急性中耳炎の診断は、鼓膜に膿が溜まっているかを観察する必要があります。鼓膜鏡や内視鏡を使えば実際の鼓膜を観察できるため、診断に必要な検査といえるでしょう。
ただし、乳幼児は直接耳の中を見られるのを嫌がる子がほとんどです。的確に検査ができるように、体動が激しいときはタオルで体を包み込んで保持します。
聴力検査は、耳鳴りや難聴といった症状があるときに実施される検査であり、正式には標準純音聴力検査といいます。
周囲の音を遮断した防音室で、高音と低音の聴こえ具合を測定します。決まった周波数の音を聴いて、聴こえている音の時にボタンを押す検査です。
乳幼児は自分で正確にボタンを押せないので、正しく測定できるのは3歳頃からです。検査が難しい場合は、診察でコミュニケーションがとれるかで難聴かを判断します。
ティンパノメトリーは、中耳に膿が溜まっているときに実施されることが多いです。
鼓膜に空気の圧をかけて耳の中の状態を観察します。鼓膜の動きや中耳の換気機能などがわかる検査です。
急性中耳炎の診断には、中耳に膿が溜まっているかを確認する必要があり、ティンパノメトリーは有用な検査方法といえるでしょう。
耳の中で圧をかけるため多少圧迫感がありますが、痛みは少ないため乳幼児でも検査できます。
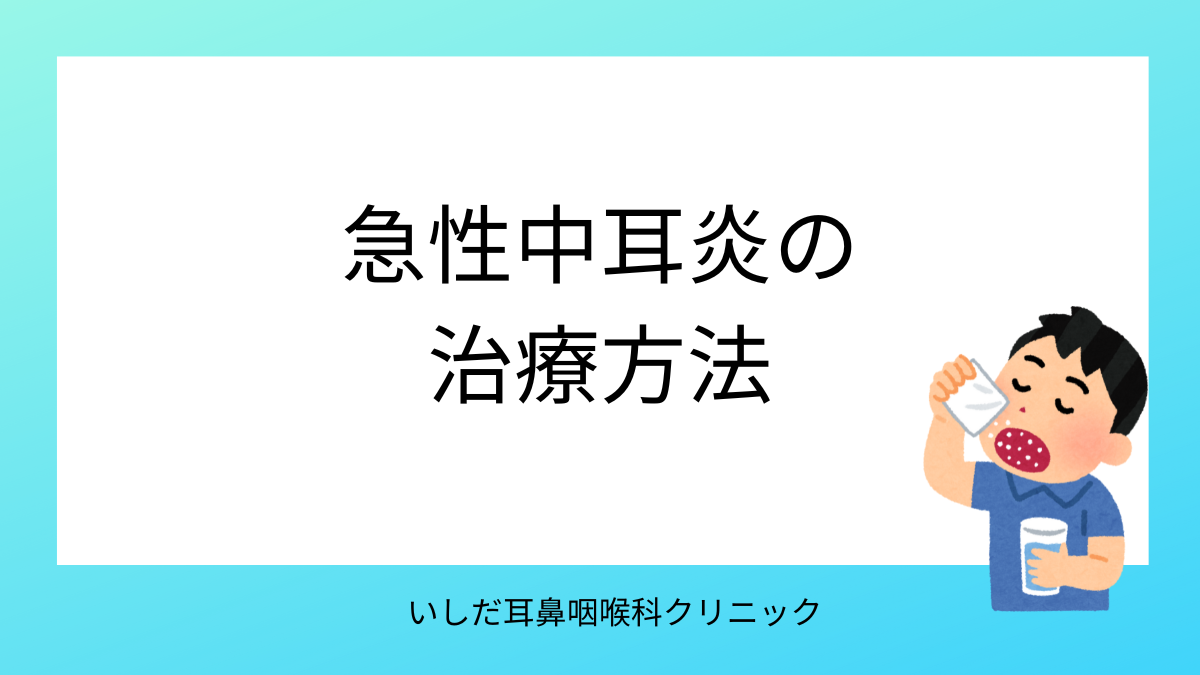
急性中耳炎は、軽症であれば自然に治癒するケースが多くみられます。
ただし、一般的な治療方法は以下のとおりです。
それぞれ詳しく紹介していきます。
急性中耳炎の治療は、まず以下の目的で内服薬を使用します。
中耳炎の原因となっている細菌(原因菌)に、有効な抗菌薬を投与すると早期に改善が期待できます。また、中耳炎になると、発熱や痛みをともなうことがあり、消炎剤は炎症や痛みをおさえる目的で使用される薬剤です。
症状が改善すると抗菌薬を飲み切らずに中断する人がいますが、原因菌を完全に死滅させるためにも処方されたものは飲み切りましょう。
耳だれの症状がある人には、抗菌薬の点耳を行います。点耳薬は、耳に直接お薬を入れるため、以下の点がメリットです。
耳だれをそのままにしておくと、難聴や慢性中耳炎に移行する可能性があります。症状がある人はすみやかに点耳薬で治療しましょう。
抗菌薬で改善しない場合は、鼓膜切開術をおこなうこともあります。鼓膜を切開し、耳に溜まった膿を排出させる手術です。中耳腔内の細菌が減少するため、抗菌薬よりも効果が期待できます。
手術では、局所麻酔をして鼓膜を切って溜まった膿を出しますが、中耳炎の症状が改善するころには、鼓膜切開した穴は閉鎖することが特徴です。
中耳炎の鼓膜切開術は外来やクリニックで実施できるため、入院せずに治療を受けられる手術となります。ただし、子どもの場合は状況に応じて、安全性を考慮したうえでクリニック内で施術を行うか決定します。
急性中耳炎は、鼻の吸引やネブライザーで鼻の炎症の改善を期待できます。鼻の吸引を行うことで、菌が含まれた鼻水や痰が中耳に侵入し、感染するという状況を防ぎます。
鼻のネブライザーは、直接薬剤を鼻の内部に噴霧する治療器具です。粘膜に直接薬剤が届けられるため、その効果により鼻呼吸がしやすい状態になります。
急性中耳炎は、鼻から耳管を通って感染が起こるため、治療として使用される鼻の吸引やネブライザーは、細菌やウイルスが通る鼻の炎症を和らげる効果が期待できるでしょう。
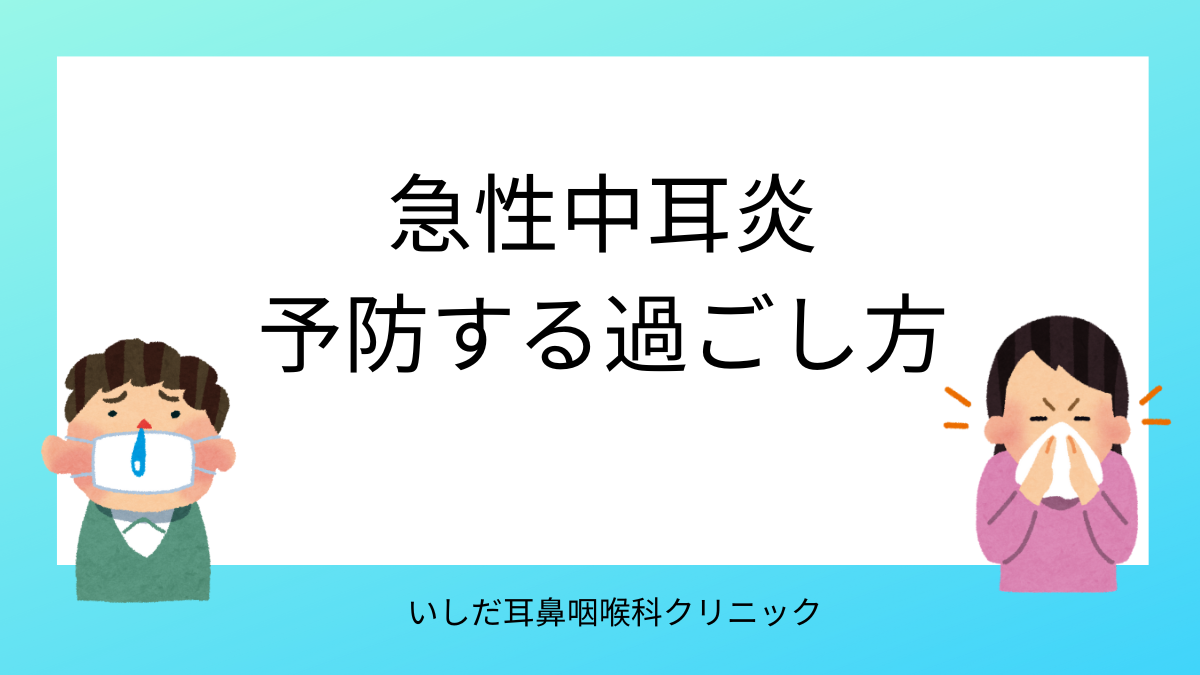
急性中耳炎を予防する日常生活の過ごし方は、以下のとおりです。
詳しく紹介していきます。
急性中耳炎は、かぜを引いてしまうことが主な原因です。かぜで鼻水に混ざった細菌が、耳管を通って中耳で感染を引き起こします。
普段からかぜを引かないように、栄養のある食事をして強い体をつくり免疫力を上げましょう。
かぜを引いて中耳炎が心配な人は、最初から耳鼻科への受診をおすすめします。急性中耳炎を発症していても、早めに治療を始められるので重症化のリスクが下がるでしょう。
鼻水が出たら、こまめに鼻をかむようにしてください。鼻水は強くかまずに、片方ずつ優しくかむようにしましょう。強くかむと、鼻水が中耳の方に入り逆効果です。
まだ自力で鼻をかめない乳幼児は、こまめに鼻を拭き、乳児用の吸引器で鼻水を吸引してあげましょう。
鼻水が出ても、すすらないようにしましょう。鼻水をすすると、耳管を通じて細菌やウイルスが中耳に入り感染しやすくなります。
特に乳幼児は鼻水が出るとすすりやすいので、できるだけこまめに吸引してあげましょう。
急性中耳炎は、まず薬物治療が多く、症状が改善してきても薬は飲み続けましょう。特に抗菌薬は処方された分を飲みきる必要があります。
症状がよくなってきたと感じても、中耳炎が完全に改善したとは限りません。抗菌薬は処方された分を全部飲みきらないと、菌が残ってしまう可能性があります。中耳炎は繰り返しやすい病気なので、しっかり完治するまで治療しましょう。
薬を飲みきって症状もなくなったら、再度耳鼻科を受診して中耳炎が完治したかを確認すると安心です。
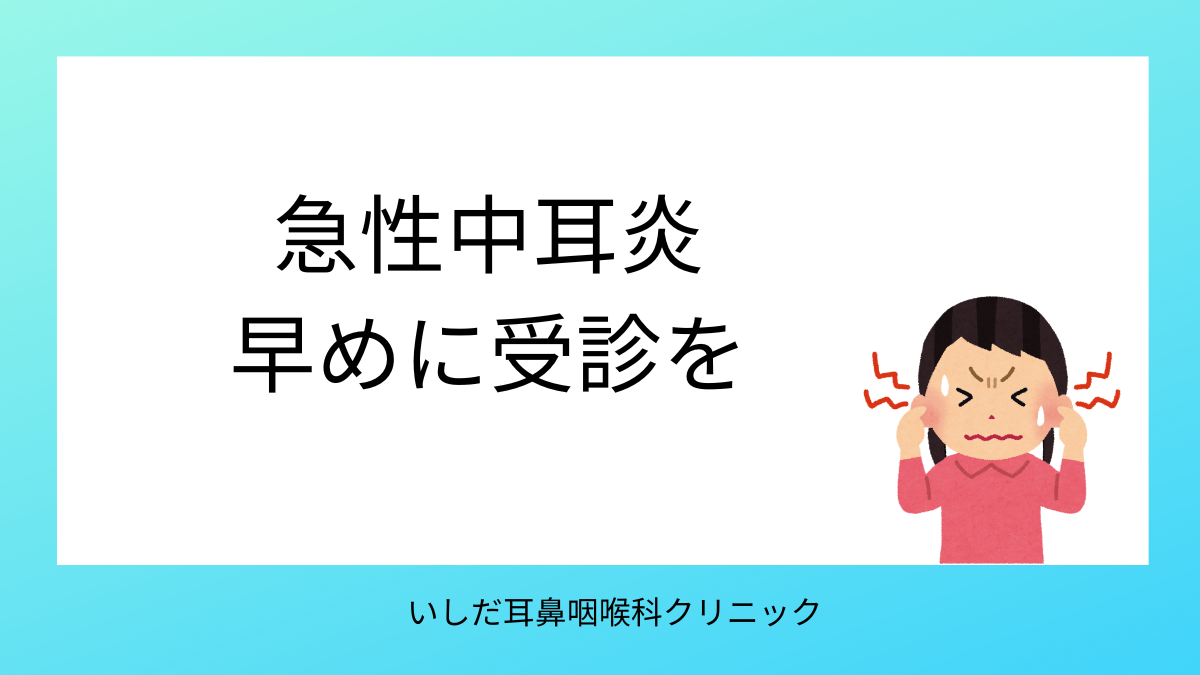
急性中耳炎とは、鼓膜のある中耳が化膿して赤く腫れて炎症を起こしている状態です。
かぜを引くと細菌やウイルスによる感染が原因で中耳に膿が溜まります。その結果、耳の痛みや耳から汁が出るなどの症状が出てくる疾患です。
軽症の場合は、自然治癒することが多く、薬物療法で改善しやすいといえます。しかし、急性中耳炎が悪化すると、手術の必要性や重症化のリスクがあるため、早期の受診がおすすめです。
かぜを引いて耳に違和感を感じる人は、中耳炎の可能性も検討してください。少しでも症状に変化が見られる場合は、辛い症状を和らげるためにも早めに耳鼻科を受診しましょう。
耳が痛い
聞こえにくい/耳がつまる/耳鳴りがする
耳ダレが出る
めまいがする