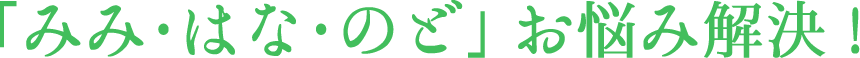
いしだ耳鼻咽喉科クリニックでは詳細な問診を行い症状・所見より原因病態を把握し、
治療の内容・期間・今後の見通しをわかりやすく説明するよう心掛けております。
 喉の痛み・かすれ
喉の痛み・かすれ扁桃腺が腫れ、発熱や喉の痛みが現れた時に、原因や治療法が分からず困る人も多いでしょう。急性扁桃炎は、細菌やウイルスが扁桃腺に感染することで発症し、治療が遅れてしまうと入院が必要になるケースもあります。
発熱や喉の痛みが続くと日常生活に影響が出やすいため、症状を認めた場合は早めに耳鼻咽喉科への受診が大切です。
こちらでは、急性扁桃炎の症状や原因、治療法について分かりやすく解説します。また、発症を予防する日常生活の過ごし方も紹介していますので、ご自身やご家族の方で急性扁桃炎に困っている人は参考にしてください。
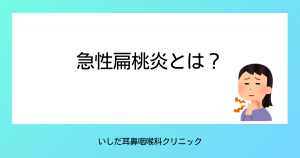
急性扁桃炎は、細菌やウイルスが扁桃に感染し、炎症を起こす病気です。
風邪と同じく発熱や頭痛、喉の痛みなどの症状が見られ、炎症が悪化すると扁桃に白い膿が現れます。
風邪よりも喉の痛みが強いという特徴があり、重症化して食事がとれない場合には入院が必要です。
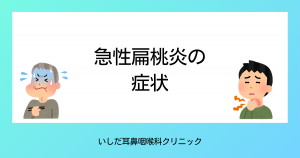
急性扁桃炎を発症すると、扁桃が赤く腫れ、以下のような症状が現れます。
飲み込み時に痛みが増すことが特徴です。特に、痛みを訴えられないお子さんは、食べることを拒む場合もあります。また、口の開きにくさやしゃべりにくさ、唾液の増加などの症状がある場合には、重症化も考えられるため注意が必要です。
症状が強く食事が摂れない時には、入院治療が必要な場合もあるため、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。
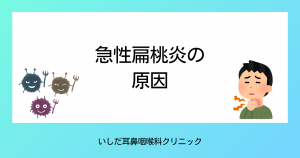
急性扁桃炎は、細菌やウイルスが扁桃腺に感染し発症します。
原因となる細菌やウイルスの特徴は、以下のとおりです。
急性扁桃炎にかかる人の3割は、細菌が原因で発症します。
炎症の原因となる細菌は、以下の種類が一般的です。
これらの中でも、溶連菌による感染が一般的です。溶連菌が原因の急性扁桃炎では、猩紅熱がみられることがあります。
*猩紅熱(しょうこうねつ)とは
猩紅熱とは、溶連菌によって引き起こされる熱のことです。
発熱とともに、喉の痛み、舌の腫れ・赤み、全身の発疹が現れます。
治療が遅れてしまうと、リウマチ熱・糸球体腎炎などを引き起こすこともあるため注意が必要です。
炎症の原因となるウイルスはさまざまで、以下の種類が一般的です。
急性扁桃炎は主にウイルスが原因で発症します。特徴的な症状は、咳と鼻水の増加です。
発熱やリンパ節の腫れ、扁桃線の膿を認める際には、EBウイルスによる発症が疑われます。長期化しやすく、最初の2〜3週間に極度の疲労感が現れるのが特徴です。
また、目の痛みやかゆみを伴う場合には、アデノウイルスによる発症も考慮されます。高熱や喉の痛みが続くのが特徴で、5歳以下のお子さんに多いです。
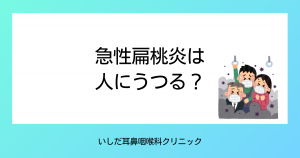
急性扁桃炎の原因は、主に細菌・ウイルスのため、人にうつる可能性があります。
主な感染経路は飛沫感染です。保菌者の咳やくしゃみを吸い込むと感染します。
飛沫は1〜2メートルまで広がるため、保菌者と接する場合は距離を置きマスクを着用しましょう。
飛沫感染する主な病原体には、以下の種類があります。
また、経口感染は病原体に汚染されたものを飲食すると起こります。保菌者の唾液が付着した食器の共有や、飲み物の回し飲みは控えましょう。
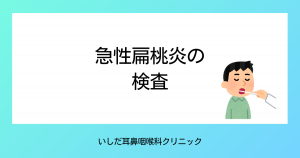
急性扁桃炎の診断には、扁桃の状態や特徴的な症状の確認が必要です。
炎症の原因が細菌とウイルスのどちらかを調べるために、必要に応じて血液検査を行うこともあります。
医師が口腔内を観察し、扁桃の状態を評価します。喉の赤みや腫れ、膿が出ていないかなどを見て、必要な治療を検討をするためです。また、首の触診を行い、首のリンパ節が腫れていないかを確かめます。
同時に、喉の痛みや全身のだるさが出ていないかなど、症状の有無・程度について問診を行います。
炎症で喉が腫れると、血液中の白血球数や炎症反応の値が増加するため、血液検査で確認します。白血球数や炎症反応の値をみれば、細菌とウイルスのどちらが原因かも特定可能です。
溶連菌の感染が疑われた場合には、溶連菌迅速検査を行います。
溶連菌迅速検査は、綿棒で喉をこすり細胞のサンプルを採取する方法です。5分程度で検査結果が分かります。
綿棒で扁桃をぬぐった液を培養し、細菌の種類を調べます。
原因となった細菌を特定し、適切な抗生物質を選ぶことが検査の目的です。
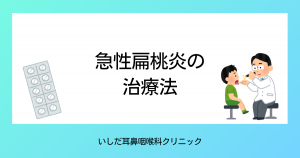
急性扁桃炎の治療は、主に薬物療法や対症療法です。
ただし、扁桃に膿が溜まっている場合には穿刺・切開による排膿、繰り返し発症する場合には扁桃腺の摘出手術が必要になるケースもあります。
細菌による発症では、薬物療法を行います。原因菌の除去や繁殖防止が目的です。ペニシリン系の抗生物質が多く使われますが、重症度や細菌の種類によっては使用する抗生物質を変えることもあります。
そのため、細菌の種類を特定する培養検査の実施は重要です。
ウイルスが原因の場合は、抗菌薬が効きません。症状をやわらげる目的で対症療法を行い、自然に治るのを待ちます。
頭痛や喉の痛み、高熱を抑える目的で消炎鎮痛薬を内服します。加えて、安静にして水分を摂ることも必要です。
喉の痛みが強く、食事が摂れないほど重症化した場合には入院が必要です。入院中は症状の強さに合わせて、抗生物質の点滴や栄養補給のための点滴を行います。
扁桃周囲に膿が溜まっている時は、排膿が必要です。扁桃に針を刺して膿を抜いたり、扁桃周囲を切って膿を出したりします。
繰り返し発症する扁桃炎は、扁桃を取り除く手術が適用されます。手術は、炎症が治っている時期に行うケースがほとんどです。
扁桃を取り除くことで細菌やウイルスが感染せず、扁桃炎の再発を防ぎ、症状も出なくなります。
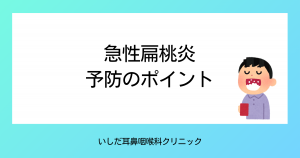
急性扁桃炎の予防には、免疫力の低下や喉の乾燥を防ぐための対策が効果的です。
疲労やストレスが溜まると免疫力が低下し、扁桃炎が発症しやすくなります。免疫力を保つためにも、適度な運動や十分な睡眠を取りましょう。また、免疫力を高める食材(果物、発酵食品など)の摂取も重要です。
急性扁桃炎の予防には、細菌やウイルスを体の中に持ち込まないことが大切です。
そのため、帰宅時や食事前には、手洗いうがいを徹底して行いましょう。
空気が乾燥すると、細菌やウイルスの繁殖力が高まり感染しやすくなります。
そのため、喉の乾燥予防として、室内の加湿やマスクの使用を心がけましょう。
タバコを吸うと、喉粘膜のバリア機能が弱まり、扁桃炎にかかりやすくなります。
特に扁桃炎を繰り返し発症している方は、できるかぎり禁煙することが大切です。
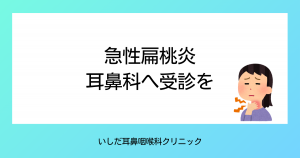
急性扁桃炎は、細菌やウイルスが扁桃腺に感染すると発症します。
発熱や喉の痛み、全身のだるさを認め、風邪との見分けがつきにくいです。人にうつる可能性があり、重症化すると入院が必要になるケースもあります。
主な治療は、薬物療法や対症療法です。適切な抗生物質を選ぶために、血液検査や培養検査を行います。
もし喉に強い痛みを感じた時には、発症の可能性を検討してください。早期に治療を受ければ、症状がやわらぎ重症化を防げます。日常生活に影響を与えないためにも、早めにかかりつけの耳鼻咽喉科を受診しましょう。
のどが痛い
声がかれる
喉の異物感・違和感